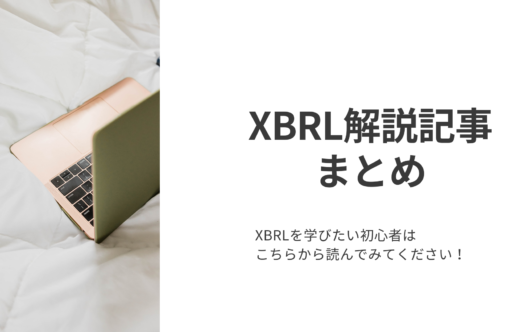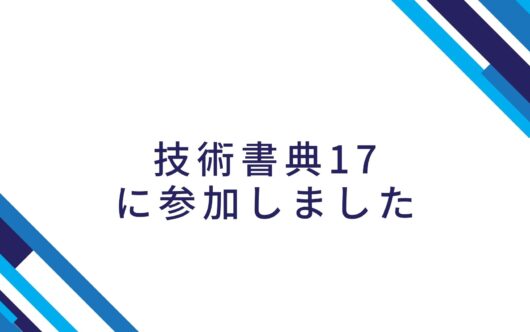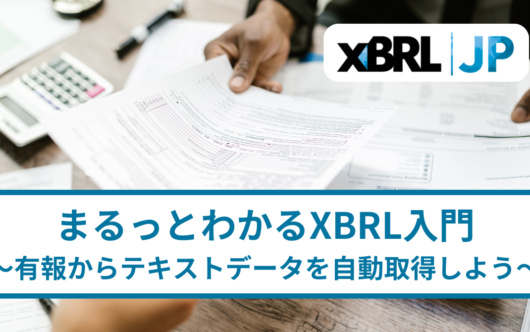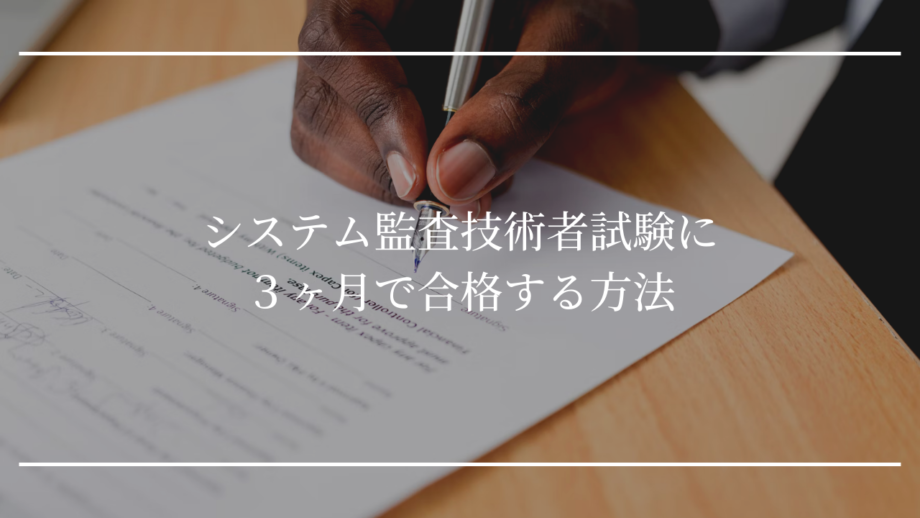
はじめに
システム監査技術者とは、システム監査を行う内部監査人や情報システム部の担当者、システム監査を行う公認会計士などが取得する資格になります。
筆者は公認会計士であることから、IPO支援や上場企業の内部統制構築支援、会計監査におけるシステム監査を行う必要性があることから、システム監査に関するノウハウを身につけるため、システム監査技術者を受験することになりました。その結果、3ヶ月程度で一発合格をすることができました。
この記事では、筆者の経験を通じて、システム監査技術者試験に合格するための方法を書いていきます。この記事を読むことで少しでも参考になれば嬉しいです。
合格までのステップ
1ヶ月目①:応用情報技術者レベルの学力を身につける
システム監査技術者技術者はIPAが主催する情報処理技術者試験の高度試験に該当するものであり、応用情報技術者レベルの知識があることが前提になっております。そのため、システム監査技術者でも午前1において応用情報技術者の午前1相当の内容の問題が出題されます。
この範囲の学習は応用情報技術者のテキストを一冊マスターすれば習得できると思います。筆者は以下の教材を利用しておりました。
ちなみに、システム監査技術者試験の午前1は、応用情報技術者試験に合格すると2年間免除になるので、応用情報技術者に合格してから受験する方が気持ちの負担が軽くなります(筆者もそうでした)。
もし応用情報技術者試験を受験していない方は、応用情報技術者試験の勉強をしてみるのも良いかもしれないですね(応用情報技術者試験の勉強法は以下になります)。
1ヶ月目②:システム監査の基本を学ぶ
システム監査技術者の合格のためには、そもそもシステム監査とは何かというのを身につける
監査のプロセスを抽象的にまとめると以下になります
リスク評価(計画立案・事前調査等)→リスク対応(監査手続の実施)→結論の報告(監査報告)
このプロセスは通常の業務で実施することは中々無いので、身につけるために苦労しがちな内容です(監査実施プロセスを理解している公認会計士がシステム監査技術者に合格しやすい理由がこちらにあります)。
システム監査の基本を身につけるためには、まずは以下の一冊を通読することがオススメです。 これを3回通読すれば、きっと基本的な知識は習得できるかと思います。
2〜3ヶ月目①:過去問の実施(午前1から午後1まで)
島田本を読み終えたのであれば、ある程度のシステム監査に関する知識が身についているかと思います。
しかし、これだけではインプットのみであり、アウトプットまでは出来ていません。アウトプットを繰り返し行うことで、知識の定着と合格のために必要な知識を身につけることが出来ます。
午前1から午後1までは、以下のような勉強を行えば、合格ラインに達することができるでしょう。
午前1(マークシート)対策
応用情報技術者試験の午前の問題をこなすことに尽きます!
以下のリンクに記載の過去問道場を用いることで、応用情報技術者試験レベルの知識を身につけることが可能でしょう。
https://www.ap-siken.com/apkakomon.php
午前2(マークシート)対策
結論から言うと、午前1と午後1の対策をすれば、午前2の対策はいらないと思います。なぜなら、午前2は非常に簡単であり、9割の人が合格できるからです。私も午前2の対策はほぼやっていませんでした。
午前2の問題の半数がシステム監査関連の問題で、残り半分が午前1の範囲から出題されます。 午後試験の対策をきちんとおこなえば、システム監査に関する範囲に関してはほぼ正答出来るようになります。すなわち、午後試験の対策をきちんと行うことが午前2の対策につながるということです。
とはいえ、午前2に多少不安があるのであれば、応用情報技術者のテキストを使って復習する程度で足りるでしょう。
午後1(記述)対策
午後1は記述式の問題になります。
こちらは大問3問から2問を選択して、問題文の内容をベースに回答していく形式になります。どんな問題が出るのかは本番までわからないため、試験が始まったタイミングでとりあえず問題をすべて眺め、自分が溶きやすそうなな問題を選べればよいかと思います。
午前1−2までの知識を踏まえたうえで、問題文に沿った回答ができることが問われておりますので、難易度は午前に比べて明らかに高いです。
問題のパターンや知識については、先述のテキストを重点的に行えば問題はないですが、重要なことは聞かれたことに答えることに尽きます。
IPAが提供する採点講評を見てるに、「解答として求めているのは○○であり、××ではない」、「どのようなリスクがあるから、どの統制が求められているかを書け」など、聞かれたことに答えることが出来ていない。問題文から課題を読み解けないような解答が多いと推察されます。そうした点では、国語力がある程度必要になるかと思いますが、国語力さえあればある程度は加点になるかと思います。。
筆者は午後1の対策として、TACのテキストを一通り読んだ後、付属の問題を2-3回解いておりました。そのうえで、聞かれたことに答えられているかという観点で見直しできるかと思います。
この程度やればシステム監査上必用な知識を解答用紙に落とし込める様になるかと思います。
2〜3ヶ月目①:過去問の実施(午後2)
午後2の特徴と合格までの道のり
午後2は、大問2つから1問選択して、そのテーマに沿った論文を2時間で書くことが求められます。これがシステム監査技術者試験で一番キツイパートです。
問題はほぼテンプレート化されており、特定のお題に対して、以下のような内容を書くことが求められます。
- リスクの把握
- リスクの評価
- それに対応する監査手続
重要なのは、リスクの把握と評価・それに対応する監査手続をセットで組み立てた答案構成をすることです。採点講評を見るに、以下のように論文としての体裁がなってない文章が多いようです。
- 問題文の趣旨または設問に沿っていない論述が散見された(問いに答えていない)
- 監査手続が不十分である(あくまで監査ということを忘れている)
- 論文の体裁になっていない(論文の構成が頭に入っておらず、アウトプットイメージが湧いてない)
そうしたことから、以下を念頭において勉強を行うことが望ましいと考えられます。
- システム監査人のマインドセットを理解したうえで、問題に取り組む
- リスク評価・リスク対応の双方の観点を持つこと
勉強方法①:答案構成について
まずは論文用の問題集を購入しましょう。筆者は以下のテキストを使っておりました。
午後2は論文形式ではありますが、いきなり論文を書くのはしんどいので、テキストに付属している午後2の問題を、以下の流れで解いてみましょう。
- 問題文を見る
- 箇条書きで良いので、答案構成を作成する
- その答案構成と解答を比較して、どういう点が監査上求められているのかを確認する(その際に、リスク評価→リスク対応のプロセスに沿って書かれているかを理解する)
- テキストの過去問を2回転する
答案構成とは、論文を書くための下書きのようなもので、論文全体の流れと問題文の解答の内容を整理するために作成します。この答案構成が非常に重要で、この質で論文の出来が決まると言っても過言では有りません。
その答案構成を作成する際には、以下の点を重視すると良いでしょう
- システム監査人の目線で答えているか?
- 起こり得るリスクの中身は何か?
- 監査人の立場でリスクを発見するための手続きは?
- そのリスクに対応するために、システム監査人が指導するべきことは?
システム監査技術者の論文は、システム監査人の立場で書くことが非常に重要であり、それが出来ていないとIPAの採点講評で毎回のように言われています。ですので、システム監査人の立場ということを忘れずに解答すると良いと思いまます。
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2020r02.html#02oct
筆者が学習する際には、以下のようにGoogleDocsに設問の下書きを書いてみて、実際の回答例と比較しておりました。
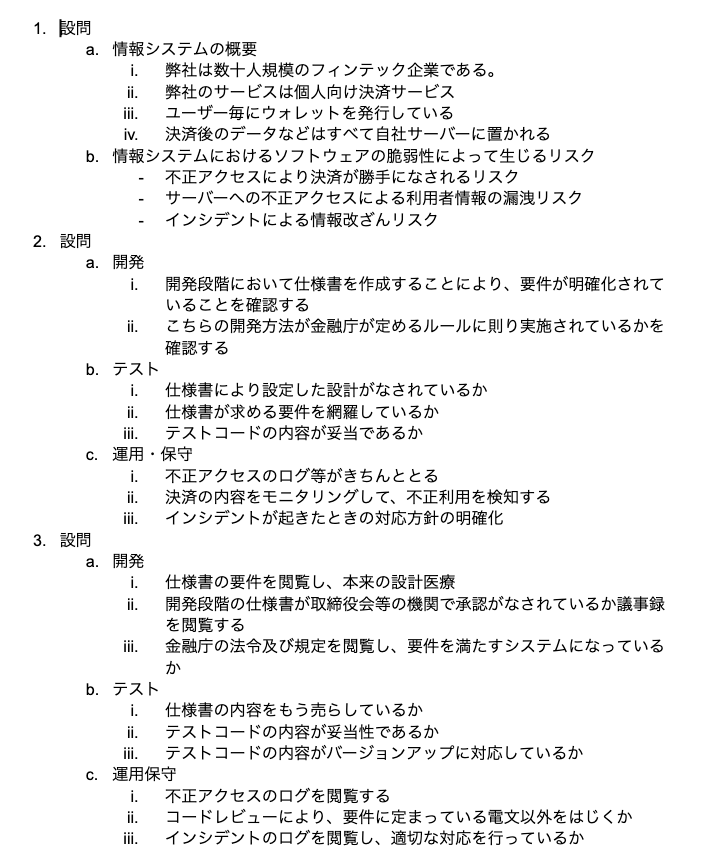
答案構成を作成するだけでも十分ではありますが、もし可能であれば、3回分くらいは論文を実際に書いてみるのが良いと思います(ぶっつけ本番で手書きに挑むのは相当しんどいですw)。
2024年12月時点では、生成AIが浸透しているので、もし可能であれば生成AIにレビューをしてもらうとよいでしょう。
さいごに
今回はシステム監査技術者試験の勉強方法について記載しました。
システム監査は監査独特の考え方を身につけるのに苦労しますが、他の分野に比較してシステムに関する専門性が問われることが少ないので、会計士などの監査業務に携わる人によっては勉強しやすいのではないでしょうか。
この記事が学習の手助けになれば幸いです。
また、弊社では、システム監査やIT統制n構築支援といった業務を行っているため、システム監査などにお困りの方は、お気軽にお申し付けください。
【2024年12月更新】システム監査技術者試験に3ヶ月で合格する勉強法
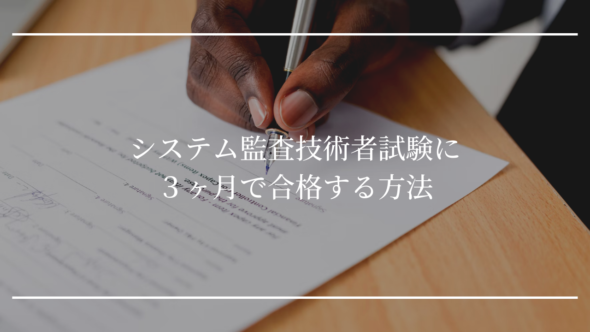
はじめに システム監査技術者とは、システム監査を行う内部監査人や情報システム部の担当者、システム監査を行う公認会計士などが取得する資格になります。 筆者は公認会計士であることから、IPO支援や上場企業の内部統制構築支援、 […]
システム監査がわかりづらい理由と、会社及び監査人が理解すべきこと
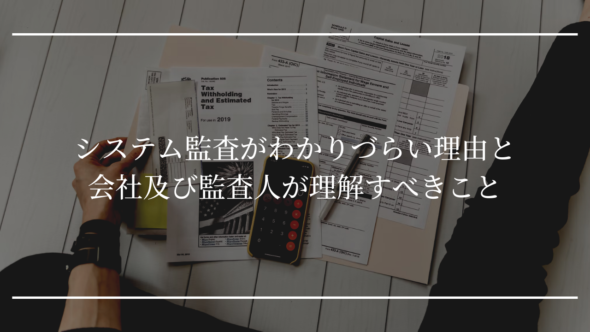
はじめに システム監査というものは会計監査や業務監査において定期的に行われている。 しかし、監査を受ける側としては「何を見たいのかわからない、見るべきポイントがずれている気がする」と思うこともあるし、監査する側としても「 […]
【内部統制基準・IT全般統制】システム監査では何のツールが使われるのかをシステム監査技術者が解説します
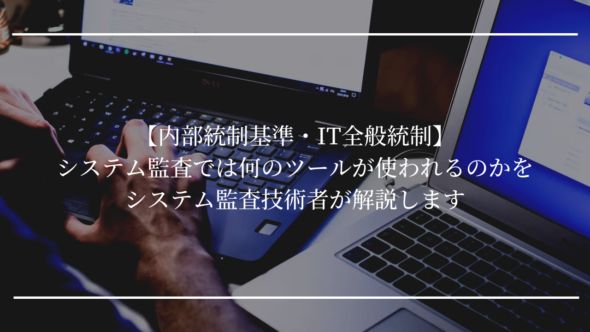
冒頭分 上場企業やIPOを目指している会社が、内部統制の整備・運用を進めるにあたって、「IT統制」という関門があります。 IT統制の検証は監査法人の公認会計士でなく、IT専門家と呼ばれる方が個別に検証を行うなど、専門性の […]
書評:『業務プロセスとつながる IT統制とIT監査 現場の教科書』をシステム監査技術者である公認会計士が読んでみた
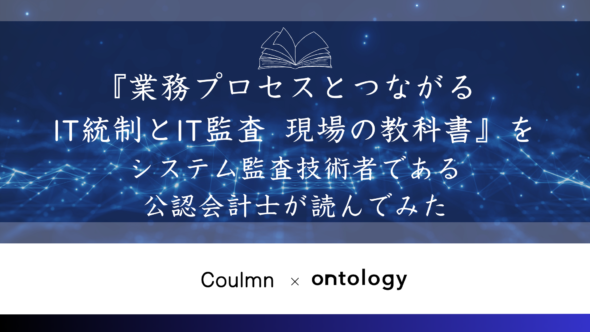
はじめに 先日中央経済社より『業務プロセスとつながる IT統制とIT監査 現場の教科書 』が発売されました。 この本は、財務諸表監査や内部統制で重要である反面、理解がしづらい分野である、IT統制とIT監査というテーマを噛 […]
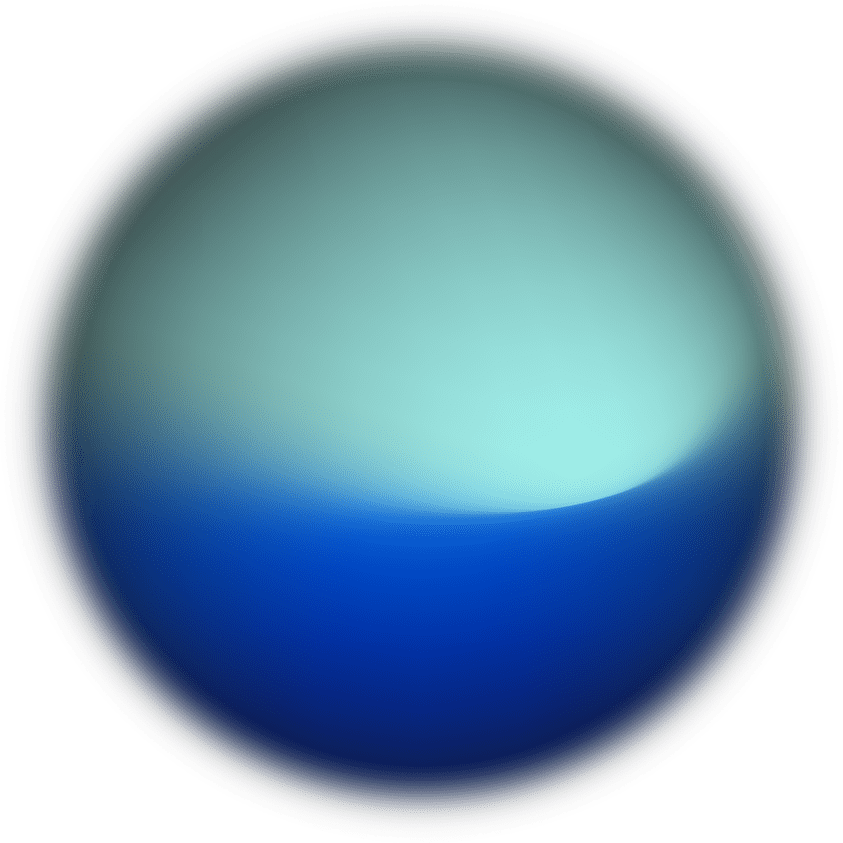

 資料をダウンロードする
資料をダウンロードする